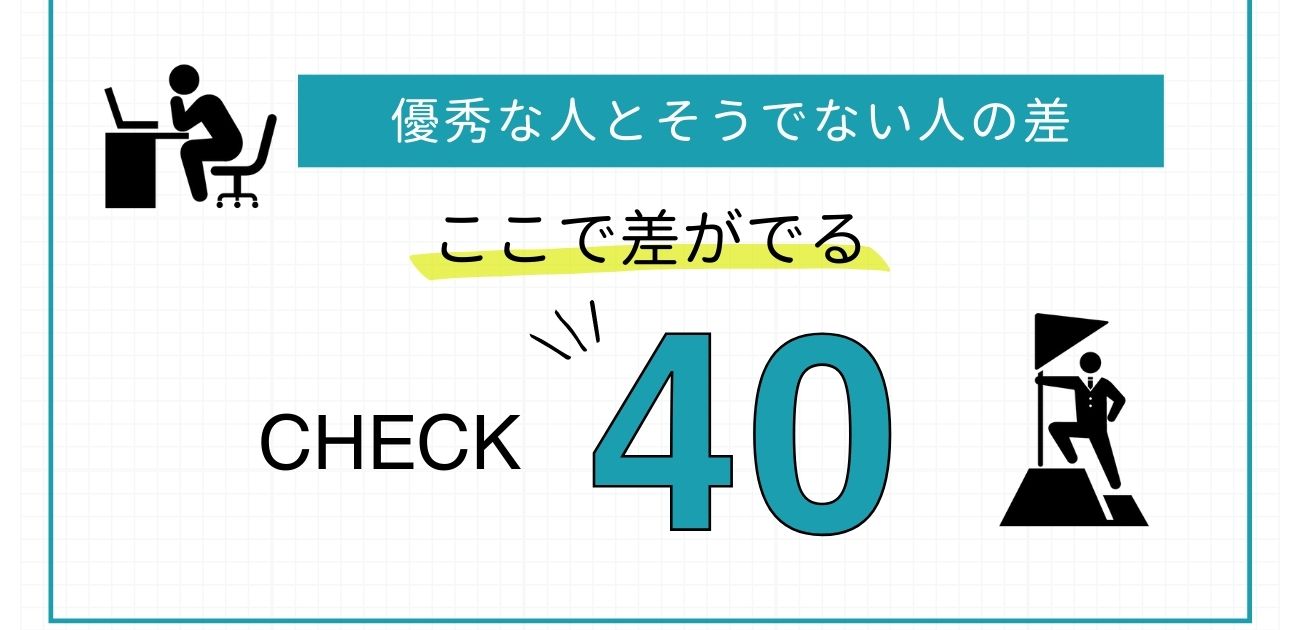あなたは「優秀な人とはどのような人」だと思いますか?
- 高い営業成績を出している人?
- 作業能力に優れている人?
- 専門知識や経験豊富な人?
- 高い役職についている人?
- 要領の良い人?
- 周囲の評価が高い人?
人の評価軸とは様々で、評価する人や環境、条件が変われば、優秀な人であるかどうかの評価は一変します。
プレーヤーとしては優秀でも、リーダーやマネージャーとしてみれば微妙といったように。
「どのような状況、どのようなタスクであっても成果を残し続けられる真の意味で優秀な人とはどのような人なのでしょうか?
最後までご覧になっていただければ【真の優秀さとは一体何であるのか?どのようなスキルなのか?具体的にどのような行動や考え方をとればいいのか?】についてお伝えしています。
この記事の要約
- 【人物像】優秀な人とはどのような人か?
- 【能力・スキル】有能な人に共通する40の特徴
- 【トレーニング】優秀な人・有能な人になるための方法
是非最後までご覧になってみてください。
1.優秀な人と優秀でない人との違いはどこにあるのか?

「優秀な人」と「優秀じゃない人」の差は「能力」や「学歴」といったものでは決める事ができません。
なぜなら上記のステータスは「あったほうが成果を残しやすい十分条件」に過ぎず、「成果を出すために必要な必要条件」ではないからです。
結論から言うと「優秀な人」か「優秀でない人」かどうかはたった3つの質問をすればすぐにわかります。
本当に優秀な人かどうかを見抜く3つの質問
優秀な人かどうかを見抜くためには、以下の3つの質問が効果的です。
有能さを見抜く3つの質問
- あなたは仕事で成果を出すために、どのような情報が必要だと思いますか?
- あなたは仕事の優先順位をどのようにしてつけていますか?
- あなたは批判される、怒られるということに対してどう思いますか?
面接の際に僕は必ず上記の3つの質問を必ず行います。
詳しく解説します。
優秀である条件①:自分のやりたいことではなく、必要な事を達成しようとしているか
では結論から言います。
優秀でない人は「自分がこうすべきだ」ということに固執することに対し、真に優秀な人は「周りが求めることを満たそう」とします。
優秀な人は「仕事を始める前に、自分が何を求められているのか?」を知る事から始めます。
何を達成すれば、評価されるのかが分かっていない状況で努力しても、無駄になる事が分かっているからです。
そのため真に優秀な人はまず以下の5つの情報を集めることから始めます。
優秀な人の5つの確認事項
- あなたは、今の職場においてどのような役割を求められていると思いますか?
- あなたは、上司や先輩はあなたに対し、何を求めていると思いますか?
- 上記を満たすために、今あなたは、どのような目標や課題を掲げていますか?
- 上記の目標や課題を達成するために、どのようなことを意識して仕事をしていますか?
- そのような意識を持って仕事をする中で、こだわっているポイントはどこですか?
「目標設定から逆算して行動する」ということはビジネスでは口酸っぱく言われていますが、ほとんどの人の場合、まずこの目標設定が自分で好き勝手に決めちゃうので上手くいきません。
目標設定は自分が決めることではなく、自分が求められる役割・ミッションから逆算して決めるべきです。
面接のエピソードトークでは話全体から「正しく目標設定するために情報を集めてから行動に移す習慣が身に付いているかどうか」を聞くようにするといいです。別の言葉で言うと素直さということもできますね。
この素直さは残念ながら学歴に反比例するので本当に注意が必要です。
優秀である条件②:優先順位をつけて仕事ができているか
優秀・有能であるための第2の条件は「優先順位」です。
残業することは基本的に非効率を助長するので、基本的に業務時間は8時間しかありません。その8時間で最大効率を出す方法、今時の言葉で言うとタイム・パフォーマンス(タイパ)を考える事が重要になります。
タイパを考えた仕事の仕方として一般的なものが以下になります。
優先樹陰の付け方
- タスクを洗い出す:必要な作業を全部リストアップする
- 重要度と緊急度で分類する(アイゼンハワーマトリクス)
重要かつ緊急 → すぐやる
重要だが緊急でない → 計画してやる
緊急だが重要でない → できれば任せる
重要でも緊急でもない → 捨てる/後回し - 成果への影響度で判断する:どのタスクがゴール達成に直結するか考える
- 時間対効果を意識する:短時間で大きな成果につながるものを優先する
- 期限を確認する:締切があるものは先に片付ける
- リソースを考慮する:自分でやるべきか、他人に任せられるかを判断する
- 3つに絞る:1日の最優先タスクは「最大3つ」に制限する
- 定期的に見直す:状況や条件の変化に応じて順位を更新する
上記に加えて、僕の場合は、以下の仕分けで仕事の優先順位を考えるようにしています。
僕の仕事の選別方法
- 成果が出るまでに時間がかかり、日々ちょこちょこしないといけない仕事
⇒部下の意識改革などの教育業務(どんなに忙しくても毎日必ず時間を取る) - ノウハウがなく、仕事がどのように進捗するか読めない仕事
⇒試してみて結果を見てから改善すべきなので、余裕を持って動き出す。 - 顧客には迷惑がかからず、最悪、同僚や先輩、上司に謝ればなんとでもなる業務
⇒忙しく過ぎる時は思い切って捨てる - 売上や顧客満足度に関わるが今の能力で準備なしで出来る仕事
⇒締め切りギリギリで間に合うようにする。イレギュラーがないので計算できるから。
仕事が上手くいかなく理由は「物理的に時間が間に合わずにタイムアップになる」か「自分の経験不足や練習不足で必要なクオリティを提供できない」の2通りしかありません。
上記の2つを意識してた優先順位で仕事を出来ていれば、予算や目標を達成できないということはほぼなくなります。
優秀である条件③:結果にコミットできているか
コミットという言葉は、少し前にかなり流行った言葉であるが実際に日本人でこの言葉を体現できたいる人は稀です。
なぜなら少しでも批判をされれば、自分の立場を守ることに固執する人が多いからです。
本当に結果を出すことにこだわるなら、自分の至らぬ点や課題を指摘してくれる人はとても貴重です。
なぜならそこを直せば結果を出しやすくなるということに気付けるからです。
少しでもネガティブな意見があると噛み付いたり、マウントを取ろうとする人には正直指導は難しいです。
「へそを曲げられたら面倒だな」って上司の立場であれば思っちゃうので。
今能力が低くても、素直で熱心な部下というのは指導がしやすいので、数年後、おお化けする可能性が高いです。それは単純に上司や先輩からのフィードバックの可能性が高いからです。
なので僕は面接やグループワークなど、議論で勝ちに行かずに、上手に負けられる人を評価するようにしています。
本当に優秀な人に共通する5つの特徴
優秀な人・有能でも仕事をしていれば失敗もするし、上手くいかない時だってあります。
しかし、1年といった長い期間で見てみれば、短期間で状況に応じた最適解を導き出し、周囲の人間からしてみれば「あの人はやっぱりすごいな」と評価に落ち着くわけです。
まとめると優秀さ・有能さとは「短期間で成果を残すことの出来る圧倒的な成長スピード(改善力・調整力)」ということができます。
優秀な人の思考の一例
では実際に優秀な人・有能な人はどのような思考をしているのか?について紹介したいと思います。
イメージしやすいように「受験」「アルバイト」「スポーツ」「恋愛」「仕事」という5つのシーンで考えてみました。
優秀な人・有能な人は【以下のような立ち回り方(戦略)を考えてから行動】します。
| シーン | 結果を変えるためのアクション |
|---|---|
| 受験の勉強戦略 | 自分が解けない問題だけ・テストに出やすい問題を集中的にやるべき。 |
| アルバイトの立ち回り | あの人がその仕事をしているなら、自分は別の仕事を探すべき。 |
| スポーツの練習意識 | 自分がしたいプレー・苦手なプレーを意識して練習しなければ上達しない。 |
| 恋愛での立ち回り | 相手がいることなんだから、相手の好みや価値観に合わせて振舞うべき。 |
| 仕事における行動基準 | 仕事は、上司や先輩、顧客に合わせて自分の行動を変えなければいけない。 |
例えば勉強で「来週試験かー。何勉強する?」という質問をして「数学で自分が解けない・ミスが多いのは、この単元のこの形式だからそこを重点的にやる。後は解説見たら大体わかるし、流しで勉強して他の教科をやるかなー」という回答であったとしましょう。
誰もが「こいつ賢いわ」と思うはずです。
一方勉強が苦手なこの場合は「数学ヤバイ。とりあえず問題集やる」という抽象度の高い回答になります。
自分がたどり着きたいゴールへの道筋をどれだけ具体的に描けるか?が重要なポイントになります。
受験やスポーツで結果を出した人が優秀・有能である傾向が多い理由
就職活動で体育会系・学歴採用が多い理由は、やはりこれまでに結果を出した人のほうが、統計的に見てもビジネスで高い成果を残す確率が非常に高くなります。
それはIQとかそういった先天的な要素ではなくて、問題解決のプロセスをより詳細的・具体的に行うノウハウを身につけているからです。
野球で「早い球を投げられるようになりたい」というスポーツの例で考えて見ましょう。
問題解決のプロセスは以下の通りです。
有能な人の問題解決プロセス
- 速い球を投げるために必要な要素を片っ端に考えてみる。【リサーチ】
- その中から自分が出来ている・出来ていない事を○・×をつける。【リストアップ】
- 自分が出来ていないことをできるようにする練習方法を調べる。【方略立案】
- その練習方法がきちんとできているか監督や先輩にみてもらう。【定性観察】
- 1週間ほど練習したら、必ず動画や球速測定をし、結果を振り返る。【定量評価】
今では素人でもYoutubeなどのSNSを見れば、有料級のコンテンツが無料で公開されていたり、球速や回転数などの器具をネットで購入する事ができます。
練習を始める前に様々な媒体で情報収集をし、様々な観点から要素をリストアップし、チェックリストをつけます。そこから自分ができていない課題を発掘し、課題に対応する練習方法を探します。そして実際に練習をし、他人や専門家から見て実際に効果がありそうかを相談し、球速や回転数などの定量データを用いて、総合的に練習の成果を確認します。
問題解決プロセスが細かければ細かいほど、質の高い練習ができます。
これまでのスポーツや趣味で高い実績を残した人ほど、こういったレベルの高い解決方法を身を持って体験しているので、社会に出た時も具体性があり、落とし込まれたアクションプランを行っていく事ができます。
優秀な人に共通する5つの特徴
ここまでをまとめると優秀な人・有能な人に共通する特徴は以下の5つということができます。
| NO | 概念名 | 優秀な人になるために必要な5つの思考 | その思考により設定できる目標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 状況整理 | 自分の知識・技能・経験レベルを自覚し、客観的に自分を分析できる。 | 設定する目標が現実的で段階を踏んだものになる。 |
| 2 | 状況把握 | 恋人や先生、上司・先輩が自分に求めてる事が何かがわかる。 | 相手が求めるニーズが分かり目指すべき目標が決まる。 |
| 3 | 課題設定 | 相手は自分に対して、どのような評価をしているのかがわかる。 | 相手の評価を通して、自分が解決すべき課題が見える。 |
| 4 | 遂行目標 | 将来的に自分がどう変われば上手くいくかがイメージできている。 | 今の自分と理想の自分の差はどこにあるのかを特定できる。 |
| 5 | 習得目標 | そのためには、どのような練習をすれば効率がいいのかがわかる。 | 目標達成のために取り組む練習ポイントが見える。 |
簡単にいえば「①:職場の中での自分の立ち位置を客観的に把握」できて、「②:上司や先輩が自分に求める・期待していること」がなんとなくわかって、そのために「③:自分が目指すべき目標や課題を適切に設定」でき、「④:目標・課題意識」を持って仕事に取り組み、「⑤:こだわり」を持って仕事に取り組んでいる。
「金持ちは争わない」という言葉は僕は本当にその通りだなと思います。
優秀な人・有能な人は、常に今の自分は完璧と思っていなくて、まだまだ伸び白がある。もっと上手くやれば成果は伸ばせると思っています。だから議論で相手を打ち負かそうとしないし、マウントも取りにいきません。
論破をしても一文の特にならないし、そもそも口げんかで勝ってなんかいいことあるの?と思うからです。
そんな時間があるなら「本を読みたい。」「実験したい。」「数値をみたい。」という思考になります。なぜならそういった生産的な時間を増やしたほうが自分の幅が広がるし、能力は上がるし、自分がとれる行動の選択肢が広がるからです。
それを自然に思えるようになれば「本当の意味で結果にコミットする」ことを体現できるようになります。
2.周囲の人に「この人有能そう」と思わせるためには

ここまでで”優秀な人・有能な人になるために必要な考え方”についてお伝えしてきました。
次のステップとして「優秀だと思ってもらうために効果的な振る舞い」についてみていきます。
採用面接(転職)や人事考課で高評価を得る上でも役立つので知って置いて損はありません。
周囲の人間に優秀だと思ってもらうための13のポイント
「優秀だ・有能だ」と感じる要素として13のポイントがあります。
あなたは以下のうちいくつあてはまるでしょうか?
13の有能度チェック
- 話し方が論理的で分かりやすい(結論から話す、要点を押さえる)
- 聞き上手でリアクションが適切(相手の意図を汲み取り、会話がスムーズ)
- 身だしなみが整っている(清潔感・TPOに合った服装)
- 姿勢や所作が落ち着いている(余裕や自信を感じさせる)
- 判断や対応が早い(即断即決できる/優先順位づけができる)
- 時間や約束を守る(信頼性がある)
- 問題点をすぐに見抜ける(本質を捉える力)
- 改善提案や解決策を示せる(ただ批判せず、前向きな案を出す)
- 数字やデータを根拠に話す(感覚だけでなく裏付けがある)
- 人に安心感を与える雰囲気(表情が穏やか、余裕がある)
- 他人の意見を尊重できる(協調性がある)
- 知識や経験を自然に織り交ぜられる(自慢っぽくなく示せる)
- 成果や実績を持っている(過去のアウトプットが評価されている)
人が優秀さを推し量る要素をまとめると「①:外見・雰囲気」「②:コミュニケーション力」「③:問題解決力・信頼性」の3つになり、上記が当てはまるほど、“この人は有能そうだ”と判断すれやすいということになります。
優秀な人と思われるために必要な”精神的な余裕”
上記の13の要素は優秀さの一部を切り取ったものに過ぎず、優秀な人・有能な人になるために最も必要なことは”心の余裕を持つこと”になります。
大事なプレゼンテーションをする時。契約のクロージングをする時。仕事で口論になってしまった時。
多くの人は早口になってしまったり、口数が多くなってしまいがちです。
そんなときほどゆっくりと話し、相手に質問を振り、会話での間を大事にする”受身のコミュニケーション”を心がける事が重要です。
攻撃的なコミュケーションを取るのは自分に自信がないから
あなたは小学生と話す時、緊張するでしょうか?
きっとないはずです。
泣かれたり、わめかれたりした時に「どうしよう」と思うことはあっても、焦ることはなく「この子にはどう接するべきか」という上位者目線で話を進める事がで来ます。
それを会話のイニシアチブを握るといいます。
では仕事というシーンで考えて見ましょう。
お金に余裕がない。人望がない。職場で評価されていない人は以下のような攻撃的なコミュニケーションをとりがちです。
そういった人は聞いてもいないのにベラベラと喋ることが多いです。
相手が話している間、「どう自分が返答しようか」ということばかり考える。
言い争いをしている時、相手の話にかぶせ気味で返答してしまう。
相手が話している時間よりも、自分が話している時間が長い。
相手を「どう説得しよう。どう納得させよう」ということばかり意識がいく。
会話の全てを合理性や論理性で善悪・勝ち負けで決めたがる。
上記のようなことをしてしまう理由は「マウントを取りたいから」です。
「相手を論破したい。相手に反論をさせたくない。だから手数を増やして圧倒したい。」といったように自分に自信がない人ほど口数が多くなります。
会話を支配するためには受身のコミュニケーションが不可欠である
一方、真に優秀な人は自分に自信があるので、会話の主導権を相手に渡します。
なぜならどんな質問がこようが「上手くいなせる」という絶対的な自信があるからです。
また自分がどのような回答をすべきかは情報があればあるほど正しく判断しやすくなるので、相手の話をよく聞いた上で決断を下そうとするわけですね。
とりあえず、最後まで相手の話をまず聞こう。
相手は今、どのような意図を持って話しているのか理解しよう。
相手は自分に対して、どのような返答・答えを求めているのだろうか。
相手と自分の考えのギャップをどうやって埋めていこうか。
この人に対しては、こういう返し方の方がいいかもしれないな。
超一流の営業は最初は自分の口数こそ多いですが、相手が食いついてきたり、気分がのってくれば、頷きや質問の比重を増やし、相手が話している時間のほうが長くなるように誘導します。
人は話を聞くよりも話すことのほうが好きなので、相手の会話量が増えるほど、より好意的な反応や態度を引き出しやすくなります。
優秀・有能な人と思われる人になるためには
しかし受身のコミュニケーションをするためには「どんな会話になっても対応できる」という圧倒的な自信がないといけません。
頭ではわかっていても「こういう質問をされたらどうしよう」とか「威圧的な態度や批判的な意見をされたらどうしても身構えてしまう」など、無意識に防衛本能が働いてしまうからです。
そこで大事なのが会話するまでの準備です。
準備にどれだけ時間を使えているかで優秀さ・有能さを測ることができる
この世のあらゆることって準備の時点で成果の質の8割はすでに決まっていることが多いです。
僕の場合は、何気ない職場での会話でも必ず目的と落としどころを持って、ネタ探しをした上で臨むようにしています。
日常会話における準備
- 上司や先輩は「次このような話を振ってくるかも」という想定をしておく
- 関係性を深めたい人の「趣味や好きなことの共通点」を見つけておく
- 「営業で話の展開はいくつ考えられるか」というパターンを全てリストアップしておく
- 「上司や先輩がしてくるだろう指示」を職場状況や作業進捗からシミュレーションしておく
- 「来週、自分の職場ではこういう問題が起きる」という職場状況から未来の予測をしておく
僕は自分の作業をしながら、同僚や先輩、上司、部下としょうもない会話をしたり、会話を盗み聞きしたりして、先輩や上司がしてくる、後輩や同僚が相談してくる内容、職場で起こり得るトラブルを想像しながら仕事をしています。
だから先輩や上司が指示してきても「そうでしょうね」となるし、部下や後輩が相談してきても「だろうね」となるし、職場でトラブルが起きても「想像していたよりも早かったな」ぐらいの感想になります。
どれだけ優秀な人でも想定外のことが起これば当然慌てます。
どんなことにも必ず兆候というものがあり、その前兆さえ事前に察知できていれば脳内シミュレーションが事前にできます。
心の余裕とは、どれだけこれまでに実績を積んだではなく、どれだけ能力や知識・経験に自信があるのでもなく、どれだけ事前に丁寧に準備できたかで決まります。
周囲から「この人は有能だ」と思われる優秀な人になるための5つの習慣
心の余裕を持って受身のコミュニケーションを取るには、とにもかくにも情報収集が肝です。
そのために必要なのが以下の5つの習慣です。
| 6 | 自発コミュニケーション | 挨拶や雑談などを自ら積極的に話しかけている。 | どんな怖い上司にもお願いができるようになる。 |
| 7 | 受動コミュニケーション | 自分ではなく相手の話す時間を増やすことをを意識している。 | 困っている時、親身になってサポートしてくれるようになる。 |
| 8 | 発展コミュニケーション | 相槌や質問・共感など、相手の話を盛り上げられる。 | 先輩や後輩、同僚から信頼・愛着を持ってもらえるようになる。 |
| 9 | 共感コミュニケーション | どんなテーマでも興味や関心を持つようにしている。 | 相手と雑談する機会が増え気付きやノウハウ、コツを教えてもらえる。 |
| 10 | 協力コミュニケーション | 相手が話しやすい空気を作ることを意識している。 | どんな性格や立場の人であっても、親密な関係を作ることが出来る。 |
普段から上記の5つのコミュニケーションを心がけていれば、どんな状況・どんな課題であっても最短距離で解決できる環境を整えておく事ができるようになります。
何かトラブルが起こってから、必要になってから行動していては成果を残し続けることはできません。
3.これから伸びる優秀な新人・若手に共通する5つの特徴

ここまでで「自分は優秀な人であるとは思えない。」あるいは「ウチの職場で有能な人材がいない」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし安心してください。
今、優秀であるかどうかなんかどうでもよくて「これから有能な人材になる」「見込みのある人材を育てる」ことが大事です。
職場・会社に必要とされる優秀な人を量産する方法についてお伝えしていきます。
人によって成長のスピードが異なる原因はどこにある?
勉強時間は少ないのに点数を取れる子、経験が浅いのにすぐに上手くなる子。何をさせても要領がいい子。
上記のような「ヒトによって成果の差が出てしまう要因」は才能ではありません。
「成果を出すためにどれだけ無駄なく、効率的に練習できるか?」にあります。
即戦力となる優秀・有能な若手・新人・アルバイトの例
ビジネスでよくいわれる「PDCAを回しなさい」という言葉。
PDCAにおいて”C(Check:チェック)”が最重要になります。
多くの場合、人が行動パターンを変えるのは、怒られた時や成績が出た時です。何か問題が起こるまで行動パターンを変えず、基本的には同じ思考原理・行動基準で普段の仕事を進めていきます。
つまり、先輩や上司が問題を発見し、怒らない限り、1ヶ月でも1年でも同じスピード、同じクオリティ、同じ優先順位で作業をし続けるということは誰かが介入しない限り、PDCAサイクルは回らないことを意味します。
しかし、本当に優秀な人・有能な人というのは飲食のアルバイトの接客業務の「水を運ぶ」という超単純作業でも意味を見出します。
有能バイトの思考プロセス
- 店長や先輩に指示されてから水を運ぶのは、作業導線がぐちゃぐちゃになり非効率だ。
- 作業導線を効率化するためには、指示される前にやっておけばいい。
- 入店音がした時点で水を取りに行く作業導線を作る。
- 他の作業をするついでにテーブルを見回り、おかわりをしておけば指示されなくなる。
真に優秀な人は無駄な行動を嫌い、どんな単純作業であっても意味というのを見出そうとします。
上記の場合は効率性で、「こうした方が早いな」とか「こうした方が無駄がない」など、すぐに伸びる即戦力の優秀なアルバイト・有能な若手は、上記のような【自分なりの回答】を持とうとします。
「今日の動きは非効率だったなー」とか「こうした方が無駄がなかったなー」など、自分自身で行動評価を数分単位で行う事ができるので、PDCAサイクルが圧倒的なスピードでぐるぐると回ることになります。
自分自身で自分の行動をチェックできるかどうかでPDCAサイクルの回転数が決まり、単純に考えてPDCAサイクルを1日でどれだけ多く回せるかで成長スピードは決まるといっても過言ではありません。
正しく成長する優秀な若手・新人に共通する5つの特徴
上記のようにPDCAサイクルを可能な限り多く回すためには”論理的思考(ロジカルシンキング)”が重要になってきますが、注意が必要です。
それは”正論を振りかざしてしまうこと”です。
高学歴であったり、能動的な人ほど、合理性や論理性という正論・持論を主張したがる傾向にあります。
- 私の考えは間違っていますか?
- こうした方が合理的であるとは思いませんか?
- それには根拠がありますか?
頭の良い人ほど、会社や職場のやり方に対して「これはやめたほうがいい」・「こうした方がいい」などの不満を持つ傾向にありますが、実際にその実現はそうたやすいことではありません。
なぜなら職場の人間関係やマニュアル・職場文化といったしがらみが存在するからです。
会社や上司、先輩たちからしてみれば「その頭の賢さを仕事に活かす」のであれば大歓迎ですが、自分たちへの不満として使われれば「頭は賢いが使いにくい奴」になります。
会社に必要とされる優秀な新人・若手に共通する”賢さと素直さの両立”
本当の意味で「賢く、謙虚に物事を考えられる人」とは以下のことを考えられる人の事を指します。
- 指示されるということは【自分と上司の考えの間にズレが生じている】かもしれない。
- 指導されるということは【自分のやり方は上司が求めるものではない】のかもしれない。
- 結果が出ないということは【自分が正しいと思うこと】が間違っているかもしれない。
- 意見がぶつかるということは【自分の表現や伝え方】が間違っているのかもしれない。
そのため本当の意味で周囲の人から「優秀だ・有能だ」と思ってもらう人になるためには、以下の5つの観察力が重要になります。
| ID | 概念名 | 自分の仕事上の癖・傾向分析 | 客観的に自分を見ることの一例 |
|---|---|---|---|
| 11 | 自己認識 | 自分は○○において□□をしてしまう事が多い。 | 自分が無意識にしてしまう癖は人に言われないと気付けない。 |
| 12 | 習慣認識 | ○○と考えがち・△△しがちと言われる事が多い。 | 無意識にしていることを指摘されるとイラッとなるけど受け入れよう。 |
| 13 | 原因認識 | それは今まで○○であるべきと思い込んでいたからだ。 | これまでこれが正しいと思ってきたが、上手くいかなかったことは事実だ。 |
| 14 | 傾向認識 | ○○を意識して生活しないとこの癖は治らない。 | 今の現実を受け入れ、相手が間違っているよりも自分が間違っていると考えよう。 |
| 15 | 修正認識 | 先輩に定期的に最近○○していると思いますか?と聞く。 | 自分は出来ているではなく、相手から見て出来ているとなるまで意識し続けよう。 |
PDCAはただ数値といった財務指標だけを見るのではなく、周りの人の反応や感想と言った非財務指標を観察し、職場の人間と歩調を合わせながら最適解を模索していく制約条件を満たした上で論理的な思考をする力が求められます。
これができれば【頭の回転が速くて、気遣いも出来る最強の新人(若手)】と周囲から評価してもらえるようになります。
4.優秀なプレーヤー(有能な部下・後輩)に共通する5つの特徴
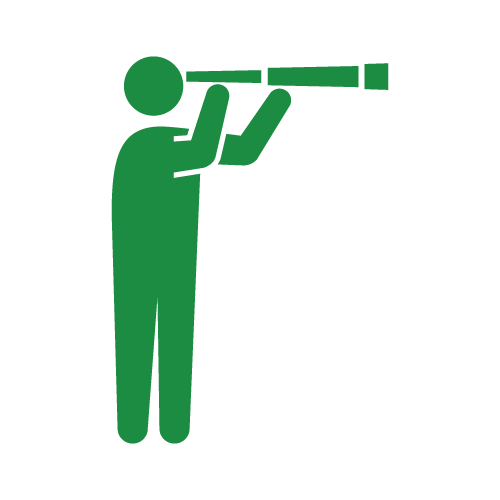
ここまでで「優秀な人とはどのような人か?」についてのイメージ像が固まってきたのではないでしょうか?
「優秀だと思い込んでいる人」と「実際に周囲の人が優秀だと評価している人」にはどのような差があり、優秀・有能な人になるために、どのような意識で仕事をしていく必要があるのかについてご理解していただけたのではないかと思います。
ここからは即実践すべきポイントについてお伝えしていきたいと思います。
プレーヤーとして優秀・有能な人材とはどのような人か
では優秀・有能な人材になるために今日から実践すべきアクションについての解説に入ります。
ここまでお伝えしてきたように優秀さ・有能さは求められる役割によって変わり、
”①:現場レベル・②:管理職レベル・③:経営幹部レベル”の3つに大きく分ける事ができます。
プレーヤーとして優秀な人材の特徴について考えていきましょう。
優秀・有能な部下・後輩に共通する特徴10個
職場で即戦力となる新人アルバイト、中途採用、新卒若手には以下の10の共通点があります。
プレーヤースキル10個
- 作業スピードが速い
→ 同じ時間でも他の人より多くの成果を出せる。 - 正確性が高い
→ ミスややり直しが少なく、信頼して任せられる。 - 自己管理能力がある
→ 体調・時間・気持ちを整えて安定したパフォーマンスを出せる。 - 学習吸収が早い
→ 新しい業務やツールをすぐに覚えて使いこなせる。 - 優先順位をつけられる
→ 重要なタスクから着実に処理できる。 - 報連相がシンプルで的確
→ 上司や同僚に必要な情報を過不足なく伝えられる。 - 協働力がある
→ 周囲と連携しながらチームとして成果を出せる。 - 改善意識を持っている
→ 与えられた仕事を「もっと効率的にできないか」と工夫する。 - プレッシャーに強い
→ 締め切りや急な依頼でも落ち着いて対応できる。 - 信頼を積み重ねられる
→ 「あの人に任せれば安心」と思われる行動を日々取れる。
プレーヤーとしての優秀さ・有能さをまとめると「速い × 正確 × 周囲に迷惑をかけない × 改善意識」の3つということができます。
プレーヤーに求められるのは計算できる戦力
プレーヤーに求められるのは「先輩や上司が戦力として計算できること」になります。
優秀な新人の恩恵5つ
- 指示が少なくて済む
→ 自分で理解して動けるので、逐一教える手間が減る。 - 業務の正確性が高い
→ ミスや確認作業が少なくなり、上司が安心して任せられる。 - 仕事の進捗管理が楽になる
→ 期日通りに仕事を仕上げてくれるのでスケジュールが乱れない。 - 周囲の教育・サポート負担が減る
→ 自分で学び、後輩にも教えられるため、チーム全体の成長が早い。 - 上司や先輩と仕事に関する話が出来る
→ 上司が気づかない無駄や問題点を拾い上げてくれる。
”誰かを雇う”・”誰かを育てる”のは自分1人では仕事が回らないからすることですよね。
まずは誰でも出来る単純作業・知識やスキルが要らない仕事から始め、ある程度経験すれば出来る仕事、職場でのルールや優先度を理解すれば出来る仕事、といったように人を育てることで任せられる仕事は増えていきます。
すると雇う側(上司や先輩)はより高次の作業に時間を使う事ができるようになるわけですが、「この仕事はこいつに任せておけば安心だ。その間にこの仕事を進めよう」と戦力として計算できる部下・後輩でなければ仕事は減りません。
スピードが速いだけで仕事が丁寧でなかったり、勝手な判断で動いたり、優先順位を理解してくれなかったりすれば、仕事ぶりを監視しなくてはいけなくなるので、安易に仕事を振ることも出来なくなります。
つまり、プレーヤーに求めるスキルとは「確実で丁寧に仕事をしてくれる計算できる戦力である」ことが第一の条件です。
職場に必要不可欠な優秀な後輩・部下の持つ特徴5つ
つまり【現場で求められるプレーヤースキル】とは、圧倒的にスピードが速い・頭の回転が速いというのは「あったら助かるな」程度なものに過ぎず、「先輩や上司、お客様がどういったことに喜んだか?」ということに対する「観察力」ということができます。
優秀な新人が持つ観察力10個
- 先輩や上司の動きを細かく見ている
→ どのように仕事を進めているか手順や工夫を吸収できる。 - 周囲の人の言葉遣いや振る舞いを観察している
→ 社内の雰囲気や人間関係を早く理解できる。 - 成果を出している人の共通点を見抜く
→ 「なぜあの人は早いのか/信頼されるのか」を盗める。 - 失敗事例から学べる
→ 他人の失敗を観察して「自分は同じことをしない」と活かせる。 - お客様や相手の反応をよく見ている
→ 何が喜ばれ、何が不満につながるかを敏感にキャッチできる。 - 現場の流れやルールを自然に把握できる
→ 言われなくても「次に何をすべきか」を行動に移せる。 - 作業スピードや効率の違いを比較している
→ 「早い人」と「遅い人」の違いを見抜き、自分に取り入れられる。 - 雰囲気や空気の変化を察知する
→ 状況に応じて立ち振る舞いを変えられる。 - 目に見えない“暗黙のルール”を観察して学ぶ
→ マニュアルに書かれていないことを掴めるので職場に早くなじむ。 - 「良い観察 → すぐ実行 → 改善」のサイクルが回せる
→ インプットを行動に落とし込むのが早い。
職場で優秀・有能だといわれる人は、本当によく周りの人の事を見ています。
- 「次は○○の作業をできるようになってくれ。」と次にどんな指導をされるか予測する。
- その仕事の手順ややり方を同僚や先輩社員のやり方を観察し、予習しておく。
- 先輩の手が空いた時を見逃さず、質問し、よくわからなかった部分を解消しておく。
- 空いている時間があれば、業務マニュアルなどを読み、知らない業務の予習をしておく。
優秀な新人は本当に周りが良く見えているので、上記のように先輩や上司が自分にどのような指示をしてくれるかの予想を立てる事ができます。
優秀な新人・有能な部下・後輩に共通する5つの特徴
ビジネスでは「よく報連相をしろ」といわれますが、どのようなことを報告し、どうなれば相談し、どのようなことを逐次、連絡すべきなのか?は先輩や上司、同僚が今どのような状況で、どのような目的で、どのような優先度を持って動いているかを観察していなければうまくできません。
先輩や上司が安心して仕事を任せられる部下・新人とは以下の5つの特徴にあてはまるということができます。
| NO | 概念名 | 作業をしながら思考すべき内容 | 作業の合間にすべき行動 |
|---|---|---|---|
| 16 | 質問の探索 | 作業をし始めたら、どんな部分でつまづくだろうか。 | 時間を見つけて、先輩に○○の質問をしておきたい。 |
| 17 | 確認の探索 | 先輩と自分との間に理解や思い込みがきっとあると思う。 | ○○とも考えられるので、先輩に○○の確認をしておきたい。 |
| 18 | 指示の予測 | 多分、先輩はこういう指示を自分にしてくると思う。 | ○○の指示をされそうだから、隙間時間に仕込みをしておきたい。 |
| 19 | 答えの模索 | もしこうなればAをすべきで、こうなればBをすべきだな。 | 作業をしながら、パターン毎にどんな対応をすべきかを考えておこう。 |
| 20 | 作業の準備 | ○○の作業の前に○○を調べたり、□□を用意しておきたい。 | ○○の作業と□□の作業の間に、時間が出来るからその時にやろう。 |
「指示されてから動き始める人」と「指示される前に十分に考えていた人」との間に作業の質に差が出るのは当然のことだといえるでしょう。
5.優秀・有能なリーダー・マネージャーに共通する5つの特徴

仕事をしていく内に「成功体験」と「失敗体験」の2つの経験値が増えていきます。
経験豊富であればあるほど、固定観念や先入観、思い込みというバイアスが強くなり”状況に応じた柔軟な行動”を取ることが難しくなります。
【成功体験への執着】と【失敗経験のトラウマ】の2つと上手く付き合うことが出来なければ、優秀な人であり続けることはできません。
自分で優秀だと思い込んでいる人にありがちな”ありがた迷惑”
プレーヤーとして多くの実績・周囲の評価を残せた人ほど、自分の業務知識・能力に対して自信を持ち、どんな時でも「こうするべきだ」と積極的にアイデアを発信し、同僚や後輩に対してアドバイスをするなど、チームの中心でいようとします。
入社当初は真面目で好感が持てる一生懸命仕事をする人であったはずが、いつの間にか「自分の事を優秀だと思い込んでいる痛い奴」と周囲の評価が一転することは珍しいことではありません。
誰もが自分なりの意図と目的を持って動いている
優秀であればあるほど、他人の仕事のやり方や考え方が目に付くようになります。
- そのやり方より、こうした方が早い。
- そのまま続ければ必ずミスをする。
- その考えでは、必ずいつかこうなる。
周りの仕事のやり方を見ていれば将来どうなるのかの想像がついてしまうので、どうしても口にしたくなってしまいます。しかし、そういった言葉を口にしてしまえば、周囲から以下のような評価をうけることになります。
自分と相手の温度差のギャップ
- 今忙しいので後でも構いませんか?
- わかりました。そうします。(あの人がどこかいけば自分のやり方に戻すけど)
- こういった考えでやっているんですけど、それは間違いですか?
相手の感情や状況を考えず、今自分の思いついた考えをすぐに言葉にしてしまう人というのは、成果を出すどころか相手のパフォーマンスやモチベーションを下げるだけの結果になる事が多いです。周囲から指摘されても「何か間違った事を言っていますか?」と考えてしまうので、たちが悪いです。
どんな行動や言葉も状況を読めずに発言してしまう人は、薬ではなく毒にしかなりません。
優秀だといわれるのに成果が伴わない人に共通する特徴
優秀さ・有能さとは「見る人が変われば評価が180度変わってしまうあやふやなもの」であり、状況に強く依存します。
例えば、あなたは上司Aの部下で、上司Aがいないときに、周囲の同僚や仕事が遅い先輩に対して、指示や指導を出して褒められたことがあるとしましょう。
その後以下のような言葉を上司から頂けたとします。
指示をしてくれて助かったよ。
○○さんに指導してくれたんだね。ありがとう。
みんなの動きに合わせてサポートしてくれてたらしいね。
しかし別の状況になれば、その評価は一転することも十分にありえます。
Aさんがすでに指示している。余計な事をするな。
今、忙しいんだから自分の作業に集中しろ。
よく考えてくれることは素晴らしいが、私の指示はよく聞いてくれ。
この場合、上記の行動が間違った可能性としては以下の事が考えられます。
- 自分より強い立場の先輩がすでにその社員に対して指示を出した後である。
- 今は作業に専念するシーンであり、まずは自分の仕事に専念すべきである。
- 方針や連携については、作業中でなく、話し合いの場ですべきである。
チームや会社のために良かれと思ってすることは非常に前向きで良いことですがそれが「ありがた迷惑」になってはいけません。
あなたがしたい行動をするのではなくて、今チームが求めている・必要な事をする。
状況にあった行動をしなければ、これまで培った知識やスキル・経験は老害と呼ばれてしまうものになってしまうのです。
優秀でないのに優秀だといわれるのはなぜか
知識や技能、経験といったものは、目標を達成するために獲得したものであり、学んだことを発揮する事自体が目的になってはいけません。「能ある鷹は爪を隠す」という諺のように、本当に優秀な人は求められなければ、以下のように無意味に知識やスキルをひけらかしません。
- この前本で知った知識を活用したい。言葉を使ってみたい。
- 非効率に動いている人を見かけたら気になる。正しいやり方を言いたい。
- 指示が的外れである時、自分が正しいと思う意見を伝えたい。
知識や技能が優れた人からしてみれば「自分の方がスキルや知識に優れているのに!なぜあいつの方が評価が高いんだ!」と思われるかもしれません。
ビジネスでは知識量よりも【使うタイミングの上手さ】が求められます。
状況に応じて”いつ何をするか”という【これまでに学んだ経験・技能・知識の活用タイミング】を考えられる人になる事が大切です。
| ID | 概念名 | 自己中な人にならないための5つのポイント | 自分の能力を活かすべき瞬間の判断 |
|---|---|---|---|
| 21 | 相手の状況 | 相手が今しなければいけないことが何か分かる。 | 今忙しそうだから、話しかけるのはやめておこう。 |
| 22 | 接触タイミング | 相手に指示・指導すべきタイミングがどこかわかる。 | 相手に話しかけやすいのはこの時間だな。 |
| 23 | スタンドプレー | 自分の技能を発揮すべき瞬間がいつであるかわかる。 | ここは自分が率先して動くべき時だ。 |
| 24 | リーダーシップ | 自分が主導権を握り、リーダーシップを発揮すべき瞬間がわかる。 | 自分の能力や知識が求められるのはいまだ。 |
| 25 | 感情の抑制 | 答えが分かっていても、自分が言うべきない時は黙っておける。 | 求められない時に、でしゃばってはいけない。 |
優秀な人でいるためには「学んだ知識や経験・技能を軸に仕事を考える」のではなく、「状況に対してふさわしい知識・技能・経験を選択する」という心がけを意識し続ける事が大切です。
6.ビジネスで求められる優秀・有能な人材の特徴
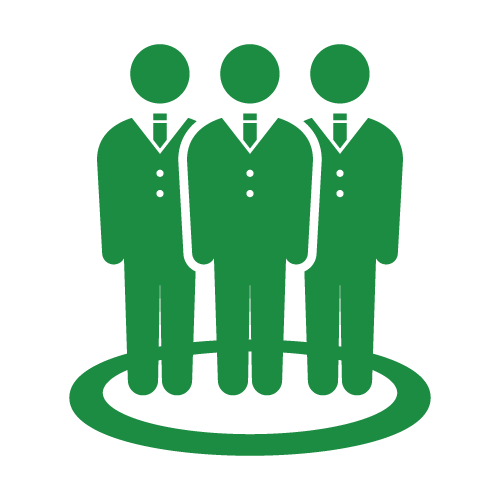
多くの実績を出せば出すほど自分の仕事はより責任の高い、多くの人が関係する業務になり、自分1人の努力では成果が出せなくなっていきます。
売上に伸び悩む経営者や管理職のほとんどが、職場の部下・同僚に対して不満を持っています。
- 何でこんなにやる気がないんだ。少しは自分で考えてくれ。
- 仕事が遅い。もっと責任感を持って欲しい。
- 能力が低すぎる。こんなメンバーでは結果を出せない。
ほとんどの会社のマネージャーは「自分はこれほど頑張っているのに、周りのメンバーに恵まれていないから結果が出せない。」という感情を持っています。
それでは成果を出し続けることは出来ません。
「こうすればこうなる」という正解が見えているのですから、自分と同じように相手を動かし【相手に自分と同じような成果を出させる】という事を目指して行動していく必要があります。
真に優秀・有能な人材の相手の行動を動かそうとする考え方
上記の話は、部下や後輩を持つ管理職になってからの話でありません。
工場であれば前工程・後工程というものがあり、アルバイトであっても他のアルバイトの動き方というものがあります。頼んでいた作業を後回しにされたり、お願いしていたことを忘れられていた時、自分の段取りが全て狂います。
優秀な人は、上司・先輩であってもお願いという形で以下のような指示をすることができます。
| 作業依頼 | この作業をしてもらえませんか? |
| 締切依頼 | いつまでにしてもらえませんか? |
| 手順変更 | このやり方に変えてもらえませんか? |
| 手順追加 | これをするようにしてもらえませんか? |
| 役割依頼 | この役割をお願いすることは出来ませんか? |
相手を意図通りに動かすことができれば、どのような仕事であっても安定して成果を出し続けることが出来るようになります。
知識や技能が高いだけの作業者と優秀な人材の差
仕事をしていると様々な課題が発生します。
- 指示をしたのにその通りにしてくれない。
- お願いした事を後回しにされる。忘れられていた。
- 仕事がいい加減で自分でやるしかなく、作業が終わらない。
- 上司が現場を理解しておらず、自分たちの話を理解しない。
他にも様々な問題が出てきます。そして「○○だったら□□の成果を出せるのに!」などの後輩や同僚、先輩、上司、職場、会社に対する不満が蓄積し、「こんな環境で成果が出せるはずない」とやる気をなくすか、転職を考えることになります。
ただほとんどの場合、どこの会社に行っても、あなたが求める理想の先輩や同僚、後輩、上司に恵まれることはなく、最終的に同じ状況になる事が多いです。
なぜなら優秀な人は、どんな職場にいこうが、自分の意図通りに相手を動かすことが出来るマネジメント術を身につけているからです。
ビジネスでは相手を動かす事ができなければ優秀だとはいえない
自分の仕事がスムーズに行くように相手を動かすためのポイントは以下の5つです。
| ID | 概念名 | 自分のお願いを断らせない5つの観点 | 相手に与えたい印象 |
|---|---|---|---|
| 26 | タスク理解 | 相手の作業負荷や進捗状況を把握した上で話す。 | あなたの作業量・作業進捗を知った上で、今お願いをしています。 |
| 27 | 人員状況 | 全体の作業スケジュールや現状を把握した上で話す。 | お願いする相手を検討した結果、あなたにお願いすることにしました。 |
| 28 | 能力・適正 | 相手の能力や適正を把握した上で話す。 | 能力や適正を考えた上で、あなたにお願いすることにしました。 |
| 29 | お願い要件 | 自分が相手にしてもらいたいことを分かりやすく話す。 | 具体的には○○の作業を、□□までにして欲しいです。 |
| 30 | 作業進捗 | 自分がどのようなスケジュールで作業をしているか共有する。 | ○○のスケジュールで動いているので、よろしくお願いします。 |
指示や指導・お願いは、相手が「承諾・受け入れて」初めて成り立つものです。
- 従った方が、自分に得がある。
- 確かに、それは自分がした方がいいと思う。
- それは職場で課題であると自分でも思う。
- そうした支援があれば、自分でも出来る気がする。
- うまくいくかわからないが、自分に出来ることならしたいと思う。
目上・目下に関係なく、お願いを聞いてもらう指示力に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
能力・知識はあるけれど、周りと上手くいかず悩んでいるのであれば、是非読んで欲しい記事です。
7.結果を残し続ける優秀・有能な人材の特徴

「成果を出すこと」と「成果を出し続ける」のでは難易度が大きく変わります。
なぜなら【役職が変われば、求められる能力が大きく変わる】からです。
これまで上手くいっていたとしても業務内容が増えたり、業務内容が変われば、求められる能力や知識も当然変わります。一度上手くいったからといって新しいステージでも上手くいくとは限りません。
真の意味で優秀な人材・有能な人材とはどのような人か
1人でビジネスをしている場合でも、会社で昇進する場合でも、仕事は常に出来ない状態から始まります。
- ビジネスが軌道に乗ったが、新しい業務が増えたので、また1から学ばないといけない。
- 昇進し、マネジメント業務が増えた。これまでやったことのない業務だ。
- 新しいプロジェクトを任せられたが、知識0で知識のある部下に指示をしなければいけない。
あなたが成功すればするほど、あなたがしなければいけない仕事は、経験がない・技能もない仕事も調べながらしていかなくてはいけないようになります。
様々な業務をしなくてはいけなくなり、全てを勉強している時間も、技能を磨く時間もありません。
【知識があるパートナーや部下に対して、相手の仕事をよくわからない状態で動かしていく】という方法を取らざるを得なくなります。
優秀・有能な人は周囲のメンバーを味方にかえる
ワーカーレベルであれば、知識や技能、経験が回りより優れていて「あなたがいうのなら」という能力の差によって、指示をしたり、お願いを聞かせることができました。
しかし、起業家や経営者、管理職は現場やパートナーの業務内容がまったくわかりません。そのため命令によるマネジメントができません。
残された方法はたった1つ。相手を信じて仕事を任せていくしかなくなります。
そこで求められる力が【周囲の人たちをファンに変えていくスキル】になります。
- こいつは仕事に一生懸命で、自分にできる限りの協力をしてあげたい。
- この人は仲間思いで、この人が考えるアイデアなら絶対に自分は協力する。
- この人には、不満も批判も素直に出来るし、それをすればより良いようにしてくれる。
優秀・有能な人材だけが持つマネジメント力とは
人は「合理的な判断で動くという部分」と「好みや価値観といった感情で動く部分」という相反する感情の総合判断によって行動を決定しています。
マネジメントに関して、様々な書籍やWEB記事、動画が世の中には存在します。
様々な理論やノウハウが紹介されていますが、大事なのは小手先のテクニックに頼るのではなく、相手の行動の変化を観察することです。
この人にこういった言葉で指示をすれば、快く承諾してくれた。
この人にはこういった振舞いで接すると警戒されなかった。
この人はこういうポイントを褒めれば、モチベーションが上がる。
この人はこういう言葉で頼み事をすれば、リーダーシップを発揮する。
この人はこのやり方で指導をすれば、反発せず、従ってくれる。
マネジメントで大事なのは、「自分が何をしたか?」ではなく「相手がどう変わったか」の変化です。
”日々の些細な変化を感じ取る観察眼”がなければ、どのマネジメントが良かったかを知る事が出来ません。
| NO | 概念名 | 人間観察における5つの視点 | 相手に合わせたマネジメント |
|---|---|---|---|
| 31 | 誇り・プライド | 相手が譲れない・こだわっていることがなにかわかる。 | この相手に対しては○○の話し方をしよう。 |
| 32 | 承認欲求 | 相手が褒められたい・評価されたいことがなにかわかる。 | この相手には○○の事を評価したり、頼ると喜ぶ。 |
| 33 | 努力・進捗 | 相手が現在目標とし、努力していることがわかる。 | この相手には○○の話題をすると話が盛り上がる。 |
| 34 | トラウマ・苦手 | 相手が避けたい・話題を避ける内容がなにかわかる。 | この相手は○○の話をすると耳を傾けなくなる。 |
| 35 | 妥協点 | 相手が妥協できる話の落としどころがわかる。 | この相手には○○をお願いすると妥協してくれる。 |
経営学は応用心理学の1つであり、マネジメントは組織行動論・行動心理学に属します。
行動の裏側に隠されている心理を理解することなしに、ビジネスでの理論・ノウハウだけを学んでも本質は理解することは出来ません。
相手の隠されている意図を読み取るという訓練がマネジメント力向上への近道です。
8.優秀な人がこだわっている仕事の終わらせ方の特徴

仕事は頭と尻をしっかりと抑える事が大切で、最後の仕上げがとても重要になります。
最後まできっちりとできなければ、事前準備と作業をどれだけ丁寧にやっていても、最大効果を得ることは出来ません。
優秀な人が褒め上手であることが多い理由
人間が一番影響を受けるもの。
それは「褒められた・怒られた・失敗した・上手くいった。」という行動から生まれる感情です。
「次はもっと頑張る」となるのか「次はそこそこで済まそう」のどちらになるかは、今回の行動の評価で決定されます。
人は”論理”ではなく”感情”で動く
例えば、あなたが一生懸命仕事をしたとしましょう。
それが失敗に終わろうが、必ずそこには学びがあります。
- 上手くいかなかったが、この取り組み自体は面白いと感じた。
- 上手くいかなかったが、こんな反応が返ってきたのが新鮮だった。
- 上手くいかなかったが、やっぱり駄目だと納得できたのでよかった。
他にも失敗から得られることは非常に多いです。
失敗は成功の母というように、10の成功より100の失敗をした方が、10年とかの単位で見たとき、成長の速度は速いです。
しかし、9割以上に人は、上記のようにプラス思考・向上心を持って動いているわけではありません。というかほとんどの場合、「頑張ったけどこうだったから」だとか「やっぱり自分の力では」といったように、努力を継続しないで済む理由を探しています。
そうしたマイナスの感情をもたせないために「行動した後のフォロー」が何よりも大切になってきます。
優秀な人が身につけている”褒める技術”
褒める・叱るという技術は相手の感情をコントロールする上で、履修必須科目といえるほど重要なものになります。
褒めるという行動は、失敗・成功に関わらず「これまでもその行動を継続してもらいたい」という時に使います。
今回、前に行っていた○○をしてくれたね。ありがとう。これからも頼むよ。
今回、上手くはいかなかったが、○○をしてくれてたね。結果は後でついてくるから、これからも頑張って欲しい。
○○してくれたこと本当に助かったよ。本当にAさんは、○○で助かっているよ。
本来、褒めるという行動は「上手くいった。成果が出た。」時に使うものではなく、相手の行動を継続させたい時に使うもので、相手にその行動をとってほしくない場合は、「結果が良くても褒めない」という選択が重要です。
次に「叱る」という行動ですが、「相手の行動を修正・禁止したい場合」に以下のように使います。
結果は出ているけど、○○になりかねない。僕としてはその行動は避けて欲しいな。
良かれと思ってしているのは十分分かっているけど、○○さんを守るためにもそれはやめて欲しい。
○○のやり方があっているとAさんは感じていると思う。しかし、こういった意図もあるので協力してくれないかな。
叱る時のポイントは、相手の人格・価値観を否定する人格否定ではなく、行動を否定する部分否定を強調することです。
「自分は相手の人格を好んでいて、職場の上司・先輩として叱っているだけに過ぎない。本来の自分はあなたを応援しているし、求めるサポートをしてあげたいと思っている。」
上記の前提があった上で叱らないと「愛の鞭」ではなく、パワハラになってしまうので注意が必要です。
優秀な人に共通する5つの褒め方
現場でのマネジメントの9割は「人間関係が占めている」といっても過言ではないと思います。
「○○の指示出したいけど、反発するだろうなぁ」だとか「○○の指導をしたらいやな顔するだろうなぁ」とほとんどの場合、正解が分かっていたとしても、それができないことがほとんどです。
社会人なんて正解が見えていても、それを選ぶことができず「誰かが変えてくれるのを待つか、緩やかな滅びを受け入れる」場合がほとんどです。本当に無能な人なんて実際はほぼいません。頭で考えている事を実行できないでいるだけです。
そこで大事なのはカリスマを身に付けることでも、圧倒的な知識・実績を積み上げることでもありません。
ただ相手を褒め、評価し、愛を持って叱るだけです。その例が以下になります。
| 項目 | 概念例 | 相手の未来の行動を変える5つの褒める技術 | 相手に次の行動 |
|---|---|---|---|
| 36 | 感想 | 自分がどれほど助かったかを伝える。 | 自分の行動は相手のためになったという自信になる。 |
| 37 | 結果 | 相手の行動で未来がどのように変わったかを伝える。 | 相手が自分は必要とされていると認識する。 |
| 38 | 学習 | 成功・失敗に関係なく、行動によって得られた事を共有する。 | 次はこうしてみようと改善の意識が働く。 |
| 39 | 課題 | 今回こういうことを自分が感じ、これに取り組もうよと誘う。 | 相手も同じ課題に取り組もうと動機付けられる。 |
| 40 | 依頼 | これからもこういうことをお願いしたいですと頼る。 | 次も助けてあげようと強く動機付けられる。 |
基本的に、1回目の行動より、2回目の行動の方が、成果は上がりやすいです。
なぜなら、1回目の行動が次につながるからです。
PDCAサイクルは、何周も回す事が大事なのであり、1回転だけのPDCAならやらないのと変わらないレベルです。
1回やってみる、わかったことがある、修正する、更に気付きを得る。よりブラッシュアップする。1回目より2回目。2回目より3回目。同じ行動をただ繰り返すのではなく、改良することが仕事では重要です。
それを成すのが褒める力です。
詳しくはこちらの記事
以下の記事では、指示・指導・お願いをする力について詳しく解説しています。
たった1日働いただけで、先輩や上司が「この子はいい子だ助けてあげたい」や後輩や同僚が「こいつの指示や指導なら聞きたい。この人についていきたい。」と思ってもらえるために非常に重要なスキルです。
まとめ:優秀な人になるための方法とその手順

ここまでで優秀な人の40の特徴についてご紹介してきました。
「人がこの人は優秀だ。・有能だ。」と評価するのは様々な軸があって、どのようなシーンであるかによって求められる能力・行動は変化することをご理解いただけたのではないでしょうか?
優秀な人・有能な人になるためには
この記事でご紹介した40の特徴はあらゆるシーン・あらゆるキャリアで活躍するための特徴まとめであり、全ての能力を習得する必要はありません。
大事なのは「今の自分にはどのような課題があって、それを解決するための能力はどのようなもので、その能力を身に付けるためのトレーニング」を知ることです。
しつこいようですが、全ての知識・技能・経験は、必要とされるから習得すべきものであって、不必要な知識や技能を一生懸命学んでも成果にはつながりません。
最短・最小経路で優秀な人になる方法
最短で今必要とされる考え方を身に付け、必要とされるスキルを習得するには、以下の手順でトレーニングプランを立てる事が必要になります。
- 自分がこれから取り組むべき解決課題は何であるかを特定する。
- その課題を解決するための能力・考え方は何であるかを知る。
- その考え方・能力を身に付けるためのトレーニング方法を学ぶ。
- トレーニングを実行し、振り返り、改良・改善を進める。
口で言うのは簡単ですが、実際には以下の問題が出てきます。
- ふわっとした目標は立てられるが、具体的にどうしたいかのビジョンがない。
- 一言でこれが課題だと決めることが難しい。
- ビジネスの知識がなく、どういった解決法があるかを知らない。
このようにこれまでの経験・知識の差によって、選べる選択肢が違ってしまうのが、優秀な人とそうでない人の差を生む原因になっています。
しかし、知識・経験の差が効率的な努力を阻害する要因であるのなら、そこを埋めてしまえばいいだけの話です。
優秀な人の思考が身に付くエクセルシートでは、以下の内容となっています。
- 全80種類の課題テキストから自分の状況に合った課題を選ぶ。
- 選択した課題の解決方法を80テキストの中から選ぶ。
- 解決取り組みの進捗把握をサンプルテキストを参考にモニタリングする。
- サンプルテキストを参考に、今回の行動を次回の行動に活かす。
このエクセルテンプレートでは、自分で課題を記入するということは一切なく、全て用意されたテキストから選択するという形式になっています。
ガイドに従って進めれば、どのようなことに取り組むべきなのかが見つけられるようになっているので、是非ご活用ください。
まとめ
何を持って優秀な人かどうかは、状況が変われば当然変化します。優秀な人かどうかは自分ではなく、相手が評価するものであるからです。
自分は仕事が早い・技能が優れていると思っていても、それは1人の作業員としての凄さであって、上司や先輩には「仕事が早いだけの使いにくい奴」と思われているかもしれません。1人で出来ることはたかが知れています。
ビジネスでは、会社や職場の売上向上やコスト削減に貢献できるかどうかが優秀さ・有能さを測る軸になります。
そのためいくら知識や技能が合っても、職場の風紀を乱したり、周りのメンバーのモチベーションを下げる人はいらないのです。
逆に知識や技能はそれほどでも、周囲を上手くまとめ、仕事の出来る部下や後輩を活かし、職場の売上を大きく変えたり、大きなプロジェクトのマネジメント経験のある人は、転職市場で引く手数多なのはそのためです。
自分が頑張って能力を磨くより、上司や先輩、同僚、後輩と上手く連携するスキルを磨いた方が手っ取り早く成果がでます。
ビジネスマンとして求められるスキルとは一体何であるのか?
それを考えるきっかけにつながれば幸いです。